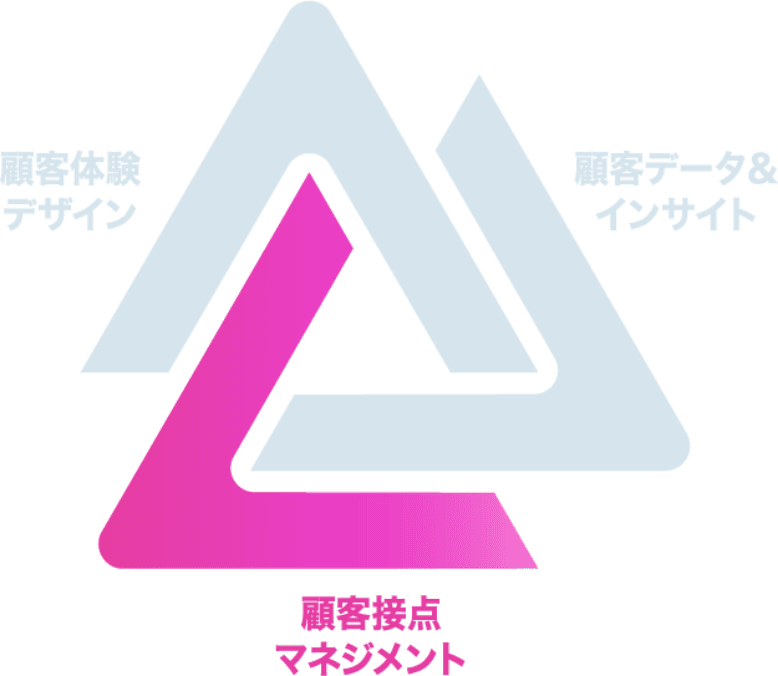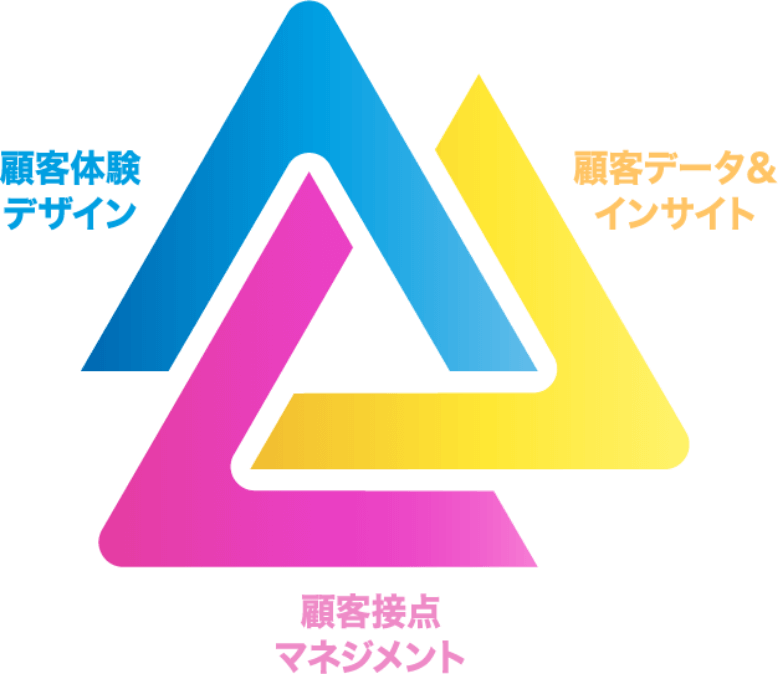© ADK Marketing Solutions Inc. All Rights Reserved.





顧客体験創造会社へ。
私たちはマーケティング・パートナーとして
企業のマーケティング活動全体を支援して
ビジネス成果に貢献していきます。
3つのソリューション領域が連携し合い
ワンルーフで統合型ソリューションを提供します。

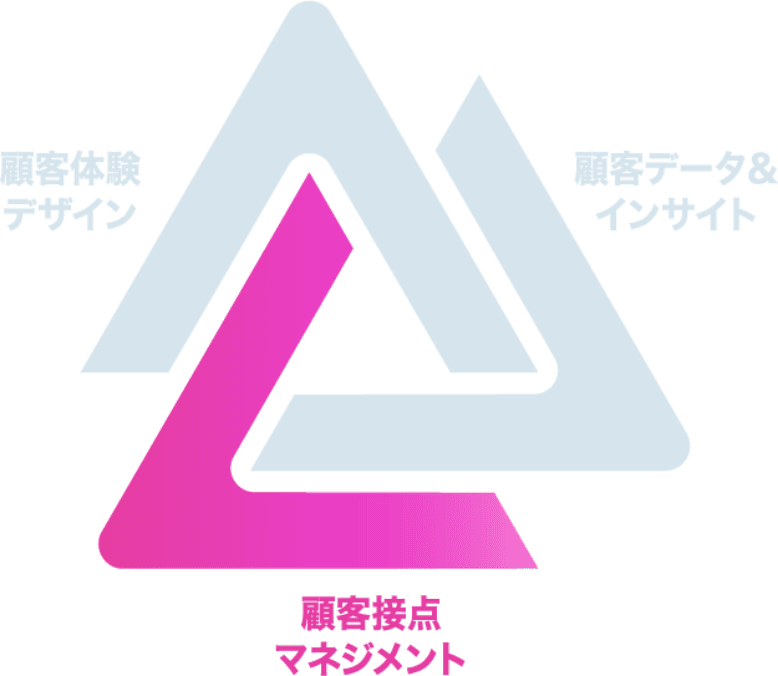

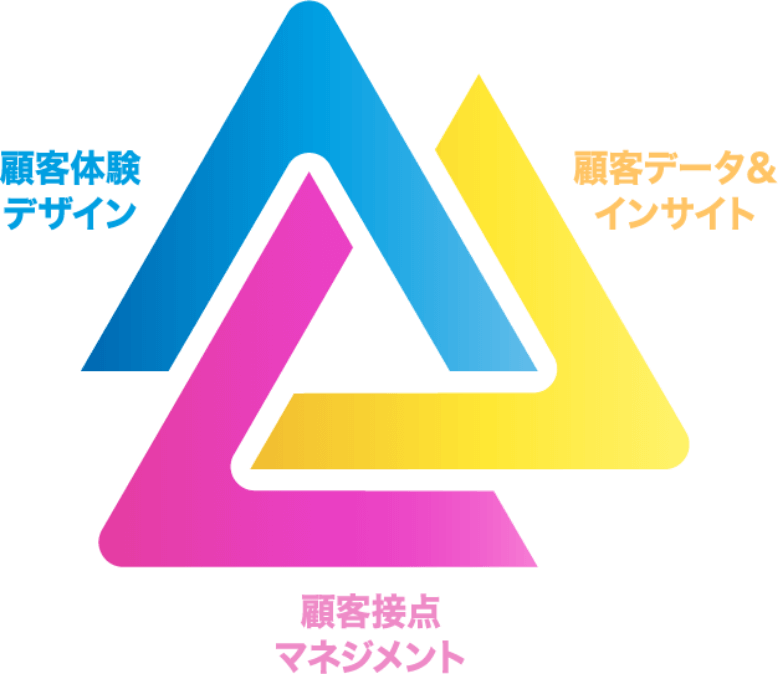
© ADK Marketing Solutions Inc. All Rights Reserved.





顧客体験創造会社へ。
私たちはマーケティング・パートナーとして
企業のマーケティング活動全体を支援して
ビジネス成果に貢献していきます。
3つのソリューション領域が連携し合い
ワンルーフで統合型ソリューションを提供します。